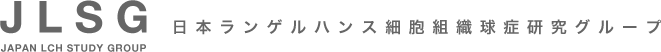第70回 最新学術情報
最近掲載されたLCH関連の論文抄録を紹介します。
1)「成人の眼窩黄色肉芽腫性疾患の全サブタイプにおいて免疫組織学的にMAPK経路活性化を認めるが発がん性遺伝子変異の検出とは関連しない」
Histological evidence of MAPK pathway activation across subtypes of adult orbital xanthogranulomatous disease irrespective of the detection of oncogenic mutations.
Detiger SE, et al. Clin Immunol. 2024 Aug;265:110299.
成人の眼窩黄色肉芽腫性疾患(AOXGD)は4つのサブタイプからなる組織球症である。さまざまな組織球性腫瘍でMAPK経路の遺伝子変異が検出されているが、AOXGDではほとんど解析されていない。MAPK経路の活性化を評価するために、28例のAOXGDおよび10例の対照黄色腫生検において、悪性腫瘍および組織球症関連遺伝子の標的領域の分析、リン酸化ERK(pERK)、サイクリンD1、PU.1の免疫組織化学染色を行った。遺伝子変異は28例中7例(25%)のAOXGDで検出された。pERKおよび/またはサイクリンD1の陽性染色は、全てのサブタイプで27例中17例(63%)のAOXGDで確認され、そのうち17例中12例(71%)には遺伝子変異は検出されなかった。対照黄色腫組織ではpERKおよびサイクリンD1染色は陰性であった。MAPK経路に変異を認めたAOXGDでは7例中5例(71%)が再発したのに対し、変異が検出されなかったAOXGDで再発したのは21例中8例(38%)のみであった。再発リスクがあるAOXGD患者を特定するためには、遺伝子解析と評価が必要である。
2)「1頭頸部の若年性黄色肉芽腫:11 症例の画像所見」
Juvenile Xanthogranuloma of the Head and Neck: Imaging Findings in 11 Cases.
Chalard F, et al. J Pediatr Hematol Oncol. 2024 Aug 1;46(6):e368-e380.
【背景】若年性黄色肉芽腫(JXG)は、主に乳児期に発生するnon-LCH組織球症である。皮膚外病変の場合、臨床所見は多様であるため診断は困難である。ここでは、さまざまな部位の頭頸部のJXG 11例の画像所見の特徴を示す。【症例と方法】頭頸部のJXG 11例の臨床データと全ての画像検査を分析した。超音波検査(US)のみが1例、MRIのみが6例、USとMRIが1例、USとCT・MRIが3例であった。全ての検査で、病変の位置と数、USでのエコー輝度と血管新生、CTでのCT値、T1強調画像とT2強調画像の信号強度、MRIでのADCと造影効果、腫瘍境界と骨浸潤といった特性を評価した。【結果】病変は9例で境界明瞭で、2例で骨浸潤が認められた。USでは、病変は低エコーまたは高エコーで、血管新生を認める例と認めない例があった。CTでは、病変は高吸収で石灰化はなかった。MRIでは、9例中8例がT1強調画像で軽度高信号または等信号、10例中7例がT2強調画像で低信号、9例中7例が低ADC、7例中7例が造影効果を認めた。【結論】年齢1歳未満で境界明瞭、T1強調画像で軽度高信号、T2強調画像で低信号、低ADC、造影効果あり、隣接骨への浸潤の可能性が示唆される病変であれば、皮膚外JXGの可能性がある。
3)「小児LCHの肺病変」
Pulmonary involvement in children with Langerhans cell histiocytosis.
Coşkun Ç, et al. Turk J Pediatr. 2024 Jul 11;66(3):323-331.
【背景】LCHの肺病変はまれで、多くは多臓器型LCHである。小児の肺LCHの臨床的特徴と治療転帰を分析することを目的とした。【方法】1974年~2022年に診断された肺LCH 37例の臨床データ、放射線学的データ、治療データを後方視的に検討した。【結果】LCH 367例のうち10%(37例)に肺病変を認めた。年齢の中央値は1.8歳(範囲: 0.4~17.7)で、男女比は2.3であった。入院時に29.7%(11例)が呼吸器症状を呈していた。画像診断では、結節性陰影から多発性嚢胞までさまざまであった。1例を除き全例が多臓器型であった。29例がビンブラスチンを含む治療を受けた。10年無イベント生存率(EFS)および全生存率(OS)はそれぞれ 47.8%、63.3%であった。2歳未満と2歳以上で比べると、10年EFSは53.3% vs. 40.2%、10年OSは58.7% vs. 68.8%であった。リスク臓器浸潤のあり/なしで比べると、10年EFSは51.9% vs. 46.3%、10年OSは51.9% vs. 73.7% であった。【結論】LCHでは肺や多臓器の障害が重大な懸念事項であり、合併症と死亡率を減らすために慎重な管理が必要である。
4)「混合組織球性腫瘍:多様な体細胞変異と標的療法への反応を明らかにする多施設共同シリーズ」
Mixed histiocytic neoplasms: A multicentre series revealing diverse somatic mutations and responses to targeted therapy.
Friedman JS, et al. Br J Haematol. 2024 Jul;205(1):127-137.
組織球症は多様なクローン性造血障害であり、腫瘍浸潤と制御不能な全身性炎症をきたす疾患である。LCH、Rosai-Dorfman-Destombes病(RDD)、Erdheim-Chester病(ECD)の3つの病型があり、これらには臨床症状、ドライバー変異、治療方針に異なる特徴がある。混合組織球性腫瘍(MXH)、つまり2つ以上の組織球症が共存する例については、十分知られてはいない。この国際共同研究は、生検でMXHと診断された例を対象に、構成病型、発がんドライバー変異、従来療法(化学療法または免疫抑制)と標的療法(BRAFまたはMEK阻害剤)に対する反応について分析した。ECD/LCH(19例)、ECD/RDD(6例)、RDD/LCH(1例)、ECD/RDD/LCH(1例)の27例を対象とした。これまでMXHで報告されていなかった変異が検出され、その中にはKRAS変異、MAP2K2変異、MAPK3変異、V600以外のBRAF変異、RAF1変異、BICD2-BRAF融合があった。反復測定一般化推定解析により、標的治療は統計的に有意に(1)完全奏効(CR)、部分奏効(PR)、または病状安定(SD)をもたらす率が高く(オッズ比[OR]:17.34、95%CI:2.19-137.00、p=0.007)、(2)進行につながる可能性が低い(OR:0.08、95%CI:0.03-0.23、p<0.0001)ことが明らかとなった。組織球症は、臨床的および分子的多様性が十分に評価されていない疾患であり、従来の治療に対する反応性は低く、標的治療に対する感受性は極めて高い疾患である。
5)「LCH関連神経変性疾患様の脳MRI所見を呈する若年性黄色肉芽腫」
Juvenile xanthogranuloma manifesting with LCH-associated neurodegenerative disease-like radiological findings.
Daifu T, et al. Pediatr Blood Cancer. 2024 Jul;71(7):e31043.
LCH関連神経変性疾患(ND)様の脳MRI所見を呈する若年性黄色肉芽腫(JXG)の2例について述べる。1例は発症時に典型的な脳MRI異常を示し、LCHに準じた化学療法から7年後に中枢神経系症状の進行とともにMRI所見が悪化した。もう1例は、JXG再発に対する救済化学療法から1年後に一時的な脳MRI変化と神経症状を認め、自然消退した。JXG関連NDに関するこれらのデータは、この疾患の今後の調査や治療介入の開発に役立つだろう。
6)「皮膚Rosai-Dorfman病:系統的レビューと治療と予後の再評価」
Cutaneous Rosai-Dorfman disease: a systematic review and reappraisal of its treatment and prognosis.
Dhrif O, Litaiem N, Lahmar W, Fatnassi F, Slouma M, Zeglaoui F. Arch Dermatol Res. 2024 Jun 15;316(7):393.
皮膚Rosai-Dorfman病(RDD)は、特徴的な臨床症状と予後を示すまれな組織球性疾患である。エビデンスに基づいて皮膚RDDを診療するために十分なデータはない。この系統的レビューは、治療法と転帰に焦点を当てて、皮膚RDDの包括的な概要を示すことを目的とした。2013年6月1日~2023年5月31日までに発表された皮膚RDDに関する論文をPubMedおよびScopusデータベースを検索した。組織学的検査で確定された皮膚RDD症例を対象とした。皮膚RDDに対する全ての治療を分析した。主要評価項目は、皮膚病変の治療反応性とし、完全奏効(CR)、部分奏効(PR)、無反応で評価した。副次評価項目は、死亡率、再発率、皮膚RDD治療に関連する有害事象とした。計118例の皮膚RDD症例を記述した87編の論文が見出された。平均年齢は48.2±16.8歳であった。男女比(F/M)は1.53であった。顔面(38.1%)の結節性(46.6%)、紅斑性(45.3%)病変が最も多くみられた。関連する血液悪性腫瘍は8例(6.8%)で認められた。最も多く行われた治療は外科的切除(51例)で、48例がCRであった。全身性コルチコステロイドは32例で用いられ20例がCR/PR、レチノイドは10例で用いられ4例がCR/PR、サリドマイドは9例で用いられ5例がCR/PR、メトトレキサートは8例で用いられ7例がCR/PRであったのに対し、10例は無治療経過観察され6例がCR/PRであった。治療無反応と独立して関連する因子は、顔面病変(OR=0.76, p=0.014)と皮膚病変の大きさ(OR=1.016, p=0.03)であった。この系統的レビューは、皮膚RDDの独特な臨床的特徴を示し、この疾患の適切な診療ついての洞察を示している。これにより、現在のエビデンスに照らして解釈されるべき治療アルゴリズムが提案され、このまれな疾患の治療に携わる医師の助けとなるであろう。
7)「小児の高リスクLCH:転帰改善のための救済療法の役割、単一施設での経験」
High risk Langerhans cell histiocytosis in children: the role of salvage in improving the outcome. A single center experience.
Sedky MSM, et al. Orphanet J Rare Dis. 2024 Jun 24;19(1):242.
【背景】小児の多臓器型リスク臓器浸潤陽性(RO +)LCHでは、第一選択治療が奏効しない例の死亡率は高い。寛解導入療法に対して疾患進行、または、初期反応は良好であったが再発し、第一選択治療が奏効しなかった例の転帰を示すことを目的とした。【症例と方法】2007年~2019年に治療された、造血、または、肝臓、脾臓病変があるRO+LCH 67例を後方視的に分析した。追跡期間は中央値6年(IQR:4~8.8年)であった。2-CdAを中心としたレジメン(2-CdABR)による救済治療を受けた時期と、受けなかった時期の2つの時期に分けられた。【結果】67例(男性 40/女性 27、年齢の中央値1.74 歳 [0.2~10歳])のうち、42例(62.7%)は第一選択治療が奏効しなかった。そのうち疾患進行が22例(52%)、再発が20例(48%)であった。疾患進行群のうち9/22例が2-CdABRを受け、そのうち5例が良好な状態で生存していた。残りの13例は2-CdABRを受けず、全例が死亡した。一方、再発群のうち12/20例がリスク臓器に再発した。そのうち8/12例が2-CdABRを受け、そのうち1例のみ良好な状態で生存し、残りの4例はビンブラスチン中心のレジメンを受け、2例が死亡し、2例が救命された。RO+の5年全生存率(OS)は65%(CI 95%:54 -78)で、無イベント生存率(EFS)は36%(26.3-50.1)であった。疾患進行群のOSは27%(14-54)であったのに対し、再発群のOSは67%(49-93)で、再発群のほうが有意に良好であった(p=0.004)。2-CdABRで治療を受けた疾患進行群のOSは56%(31-97.7)であったのに対し、2-CdABRを受けなかった疾患進行群のOSは8%(2-51)で、2-CdABRで治療を受けたほうが有意に良好であった(p<0.001)。一方、2-CdABRで治療を受けた再発群のOSは38%(13-100)であったのに対して、2-CdABRを受けなかった再発群のOSは74%(53-100)で、有意差はなかった(p=0.7)。【結論】RO+の生存率は依然として低い。疾患進行群は再発群に比べて予後が悪い。疾患進行群で2-CdABRで治療されたかった例の転帰は極めて不良であった。再発群では2-CdABRで治療されなくても予後は悪くなかった。
8)「LCHの病態マーカーとしてのAXL高発現骨髄細胞の増加とmTOR阻害のランゲリン発現依存性」
Increased AXL(high) myeloid cells as pathognomonic marker in Langerhans cell histiocytosis and Langerin expression dependence of mTOR inhibition.
Olexen CM, et al. Clin Immunol. 2024 Jun;263:110203.
LCHは炎症環境下でさまざまな臓器にランゲリン(CD207)とCD1aを発現する病的組織球の集簇を特徴とする。LCHの病的前駆細胞の起源については広く議論され、単球と樹状細胞前駆細胞(DC前駆細胞)が重要な役割を果たしている。驚くべきことに、活動性LCH患者のCD11c陽性分画でチロシンキナーゼ受容体AXL高発現細胞の増殖が見られ、この細胞も病的特徴であるCD207およびCD1aを発現していた。さらに、単球を炎症性サイトカインや活動性疾患患者の血漿で処理すると、AXLを高発現するランゲルハンス様細胞が得られた。興味深いことに、単球のランゲルハンス様細胞への分化の初期段階でmTOR経路を阻害すると、病的特徴のLCHプログラムが促進され、NOTCH1誘導と伴にCD207発現が大幅に上昇した。AXL高発現はLCHの強力な病的マーカーであり、ランゲリンおよびNOTCH1発現はmTOR経路の阻害に依存する。
9)「心臓病変を伴うErdheim-Chester病の臨床像と治療反応」
Patterns and organ treatment response of Erdheim-Chester disease with cardiac involvement.
Miao HL, et al. Heart. 2024 Jun 17;110(13):899-907.
【目的】大規模コホートにおける継続的な追跡調査により、解明が進んでいないErdheim-Chester病(ECD)の心臓病変の治療反応を評価する。【方法】2010年1月~2023年8月に当センターで診断された心臓病変を伴うECD患者の臨床データを後方視的に分析した。心嚢液貯留とPET検査を統合して心臓病変の治療反応を評価した。【結果】計40例が対象となり、年齢の中央値は51.5歳(範囲: 29~66歳)、BRAFV600E変異を56%に認めた。最も多い画像所見は、心嚢液貯留(73%)、右心房浸潤(70%)、右房室溝浸潤(58%)であった。評価可能な21例中、18例(86%)が心臓病変の治療反応を示し、5例(24%)が完全奏功、13例(62%)が部分奏功であった。心嚢液貯留の完全奏功率は33%、部分奏功率は56%であった。心臓腫瘤の治療反応についは、33%がPRを示した。PET検査での反応については、完全奏功が32%、部分奏功が53%であった。心嚢液貯留の反応性とPET検査での反応性には相関関係があった(r=0.73 [95% CI:0.12~0.83]、p<0.001)。追跡期間の中央値は50.2か月(範囲:1.0~102.8か月)であった。推定5年全生存率は78.9%であった。無増悪生存期間の中央値は59.4か月(95%CI:26.2~92.7か月)であった。BRAF阻害剤を投与された例は、第一選択治療かどうかにかかわらず、治療反応がより良好であった(p=0.037)。【結論】心嚢液貯留とPET検査での反応の両方を考慮してECDの心臓病変の治療反応の評価を行い、これら2つの指標に相関関係があることを明らかにした。BRAF阻害剤は、第一選択治療かどうかに関係なく、心臓病変の治療反応を改善する可能性がある。
10)「眼病変組織球症の診断のための血漿中細胞遊離DNA」
Plasma-Derived Cell-Free DNA for the Diagnosis of Ocular-Involving Histiocytosis.
Francis JH, et al. Ophthalmol Sci. 2024 Apr 15;4(5):100530.
【目的】循環腫瘍DNA(ctDNA)は多くの癌において血漿中に放出され、非侵襲的診断などの臨床応用が可能である。組織球症は、主にMAPK経路の遺伝子変異による骨髄性組織球のクローン増殖によって生じ、ctDNAを用いた配列解析で検出が可能である。ただし、眼病変組織球症は診断が難しいことが多いため、診断が遅れ、繊細な眼構造の侵襲的な生検が必要になる。この研究は、血漿中ctDNAの配列解析により、眼病変組織球症を非侵襲的に診断できるかどうかを判断することを目的とした。【研究デザイン】単一の三次がん紹介医療施設。【研究対象】眼病変組織球症でctDNA配列解析を受けた成人24例。【方法】デジタルPCRによるBRAFV600E検出や次世代シーケンシングを用い、当センターへの初回受診時のctDNAを解析し、変異アレル頻度を測定した。患者の年齢・性別、臨床的特徴、腫瘍組織の配列解析から特定された発癌性変異を分析した。【主要評価項目】血漿中ctDNAによる組織球症関連ドライバー変異の検出可能性。【結果】眼病変組織球症の患者の初診時に採取した血漿でctDNAの配列解析を行ったところ、14例において組織球症のドライバー変異(BRAFV600E [10例]、KRAS [2例]、ARAF [1例]、MAP2K1とKRASの共存 [1例])が検出された。循環遊離DNAで見つかった変異は、腫瘍組織の配列解析で変異が特定された11例中11例で全て一致していた。ctDNAでドライバー変異が検出されなかった10例のうち、腫瘍組織の配列解析で、3例にはctDNA配列解析では検出できない変異(CBL変異やキナーゼ融合)を認め、3例は変異を認めなかった。残る4例では、腫瘍組織の配列解析において、ctDNAでは検出されなかった変異(BRAF [2例]、MAP2K1 [2例])を認めた。ぶどう膜浸潤のある例は、ctDNA解析で変異が検出されることが有意に多かった(P=0.036)。【結論】このコホートでは、眼病変組織球症の大多数で血漿中ctDNAが検出され、診断に役立った。このことは、眼病変組織球症が疑われる場合(特にぶどう膜に病変がある場合)、非侵襲的な血漿中ctDNA分析が、繊細な眼球構造の侵襲的な生検を回避するのに役立つ診断手段であることを示唆している。